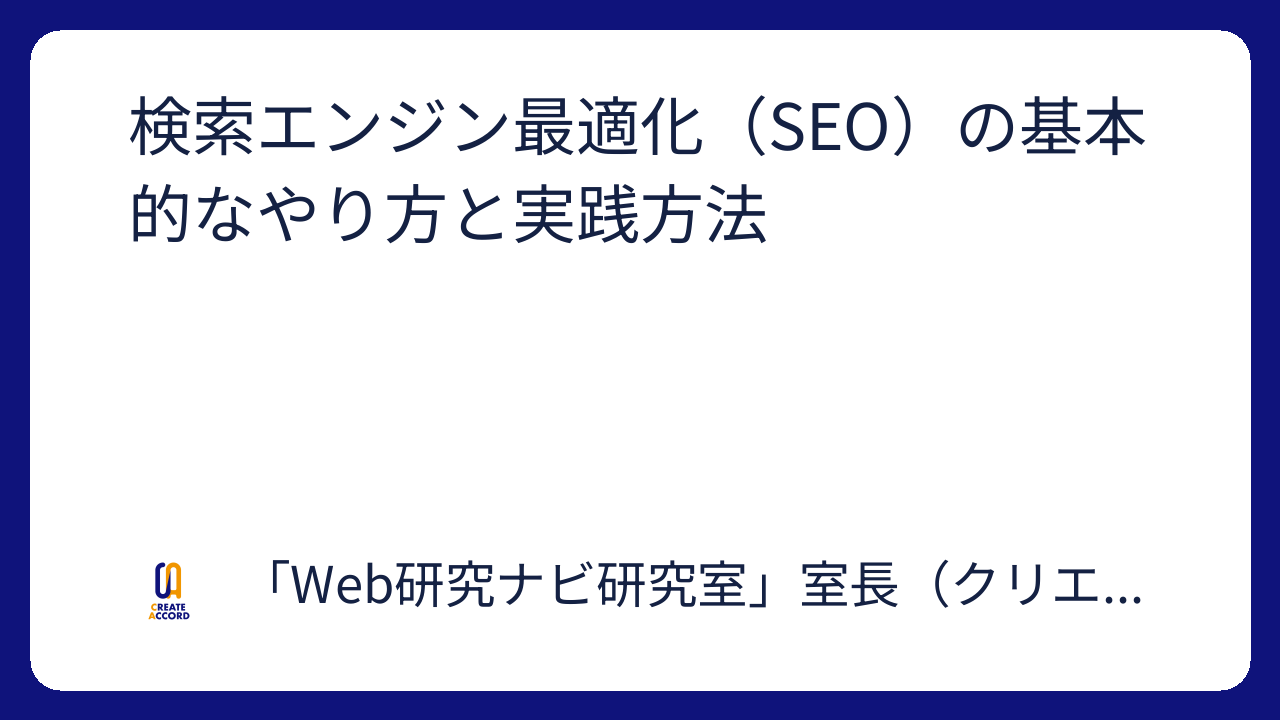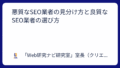SEOの基本について、検索エンジンに評価されるための基礎知識から、具体的なやり方、成功に繋げる考え方までを解説します。
この記事は、専門的な用語の解説も含まれることから、じっくり読むコンテンツとなっています。目次機能をご活用いただきながら、ゆっくりと読んでいただけましたら幸いです。
- SEOの基本的なやり方についてお話しする前に
- SEOの基本的なやり方1「SEOに取り組む前にするべきことができているかを確認する」
- SEOの基本的なやり方2「検索エンジン最適化、検索エンジンマーケティングはWebマーケティングの施策(手法)の一つでしかないことを心得る」
- SEOの基本的なやり方3「SEOに取り組む」(ただし、SEO自体はできることが限られていること、成果が実感できるとは限らないことを留意する必要がある)
- 具体的にどのように対応するのか
- SEOができても成果が出るとは言い切れない……
SEOの基本的なやり方についてお話しする前に
こんにちは。
「Web研究ナビ研究室」の室長、クリエイトアコードです。
今回は、SEO(検索エンジン最適化)についてのお話です。
2014年から、ホームページ(Webサイト)制作とSEO(検索エンジン最適化)、SEM(検索エンジンマーケティング)に取り組んできて、「SEOについて取り組むためには、SEOの基本的な考え方について把握することが大切」だと強く感じています。
そのため、SEOのやり方についてお話しする前に、基本的なやり方について説明してから、基本的なやり方について説明していきます。
SEOの基本的なやり方1「SEOに取り組む前にするべきことができているかを確認する」
最初にSEOに対する考え方を見直してみませんか?(SEOの本質的な考え方について理解する)
SEOの解説記事を見ると「たくさんやらなきゃいけないことがある……!」と思いませんか?
これはSEO以前に必要なことも、SEOじゃないこともまとめて「SEOとしてやらなきゃいけないこと」として語られているからなのですが、まずは「SEO」という言葉の意味について触れてみましょう。
SEOは「Search Engine Optimization」の略称であり、日本語にすると「検索エンジン最適化」になります。
英語の訳にある通り、SEOは「技術を使って検索エンジンに合わせてWebページを最適化すること」です。検索順位の上位を目指すことではありません。
SEOという言葉の意味については以上ですが、実際にどのように取り組むのか。
下記の順番通りに取り組むことをお勧めします。
1.検索エンジンマーケティング(SEM)に取り組む
検索システムの性質上「検索するユーザーがいて成り立つ」ものなので、検索するユーザーに向けて最適化する都合上、検索エンジン最適化の前にマーケティング戦略を立てることが必要になります。
検索エンジン最適化の前に行うマーケティングとして「検索エンジンマーケティング(Search Engine Marketing:検索結果ページ経由での流入を増やし収益につなげること。SEMと略される)」があります。
SEOに着手する前に、検索エンジンマーケティングに取り組むことで、必要とするユーザーに向けたコンテンツの作成が作りやすくなります。
英語の訳から見ても、検索エンジン最適化と検索エンジンマーケティングは別物なので、混同しないように気をつけてください。
2.「良質なホームページを作る」ことに取り組む
立てたマーケティング戦略に合わせて情報を整理して分かりやすく伝えるためのホームページ(Webページ)を作りましょう。
このように、求めているユーザーに合わせて情報を整理して分かりやすく伝えることのできる「良質なホームページ(Webページ)」を作ることは、SEOに取り組む前提条件と言えます。
3.検索エンジン最適化(SEO)に取り組む
検索エンジンマーケティング(SEM)に取り組み、良質なホームページを作る(整える)ことができたのなら、ここで初めて検索エンジン最適化(SEO)に取り組んでください。
こうすることで、スムーズかつ迷いなくSEOに取り組むことができます。
【まとめ】SEO以外の要素も含めて、まとめて「SEO」「SEO対策」として考えることをやめることから始めてみませんか?
確かに「やらなきゃいけないことは全部」ではあるのですが、これらの要素を一緒に「SEO」「SEO対策」として考えるのなら、それは様々な専門領域を全部ひとりでやっているようなものです。
それぞれ分けて考えた方が分かりやすいし、計画も立てやすいので、まずは、それぞれ段階を決めて取り組まれることをお勧めします。
次に「SEOに取り組む前にするべきことができているか」を確認しましょう。
「キーワードの最適化は?」「HTMLタグの最適化は?」「リンクの最適化は?」と色々と見てきた方なら、特に疑問に思われると思います。
SEOの専門家でも様々な見解があると思われますが、今までのホームページ(Webサイト)に関わってきた経験とSEO・SEM(検索エンジンマーケティング)の経験から、当方としては「SEO以前にすることが多いのでSEOとして本当にしなければいけないこと(やること)は実は多くない」と考えています。
例えば、下記の要素はどれも「SEO以前にすべきこと(やること)」です。
何故なら、下記の要素は、多様なユーザーにとって必要なことだったり、ページを作る上で自然に対応できることでもあり、少なくとも検索エンジンだけに対して行うべきではないからです。
もし、下記の対応ができていなかかったら、最優先に対応し、できているが成果につながらない場合は、見直しをしてみましょう。
最優先に対応すべきこと(状況により、元々の設計から見直しを図る必要がある)
- キーワードの最適化をする
検索するユーザーに合わせた検索キーワードを想定できているか、コンテンツをテーマ(キーワード)の通りにしているかを確認しましょう。このようになっていない場合は、検索結果に表示されずにユーザーがコンテンツを見ることができないリスクがあります。
すぐに対処が可能なものであり、ユーザーにとっても良くないので対応するもの
- リンク切れを修正する
ユーザーに向けて「分かりやすい」内容の情報を記載しようと思ったら、自然に対応できるはずのこと
- タイトルタグ(title)、H1タグにキーワードを含める
一例ではありますが、無意識に用語や名称などを省略して書いてしまうと、知識や経験のないユーザーにとっては「分かりにくい」ものになってしまっているはずです。ターゲットユーザーの目線でホームページ(Webサイト)やページを見て、分かりやすく、データや根拠がはっきりしていて納得や理解がしやすいものになっているかを確認してみましょう。
優先度は高いが、内容により「ホームページ(Webサイト)制作」の知識と技術が必要になる場合があるので、状況により専門家に相談・対応を依頼した方が良いこと
- HTMLタグを正しく使用したマークアップをする
- スマートフォンの最適化をする
- 内部リンクの最適化をする
- 画像に対してalt属性を正しく記述する
- 画像のファイルサイズを小さくするなどでページ表示速度を改善する
- モバイルフレンドリーにする
- WebサイトをSSL化(HTTP化)する
誰かから「この記事はとても参考になった」と紹介される(リンクを貼ってもらう)こと、関連性の高い記事同士を自然な文脈でリンクをつなぐこと、Webサイトの様々な個所で「このページで解説しています」のような形でリンクを貼って紹介することのように、ユーザーに過不足なく情報を与えようと行動すると、重要な記事ほどリンクが集まる傾向にあります。
上記はSEO以前に取り組むべきことであり、ユーザーにとって見やすく情報を整えることも、良質なホームページ(Webサイト)を制作する(整える)」のに必要なことですが、これらの内容については、ホームページ(Webサイト)制作に関する知識や技術が必要になります。調べながら対応することや既に対応しているツールやサービスを利用することでも対応はできますが、実際に問題なく対応できているか、知識と技術を持っている方のチェックがあると安心です。
優先度は低くないが、「ホームページの運用」の話であり、今すぐ改善を図れるものではないので、運用しながら取り組んでいくこと
- クロール頻度の高いページにリンクを貼る
- サイトの更新頻度を高める
検索エンジンがクロールしてくる、つまりはユーザーにとって需要が高いといえるページの品質をより高めること、サイトは常に最新の情報にしておくことは検索エンジンのためではなく、ユーザーのための行動です。
SEOの基本的なやり方2「検索エンジン最適化、検索エンジンマーケティングはWebマーケティングの施策(手法)の一つでしかないことを心得る」
Webマーケティングの施策(手法)は、広告運用・SEO(検索エンジン最適化)・SEM(検索エンジンマーケティング)・SNS運用・メルマガ・公式LINEなど、様々なものがあります。
SEOも、SEMも、Webマーケティングの施策(手法)の一つでしかありません。
そして、SEM(検索エンジンマーケティング)は、検索エンジンのアルゴリズム(システムの計算方法、処理手順)の変化の影響を受けやすく、また、「ユーザーが検索する」ことで成り立つことから、市場の変化の影響を受けやすいです。
- たまたま景気がものすごく悪かった時期に重なってしまったら?
- Googleのシステムに不具合があったとしたら?
- 売れる時期と売れない時期は毎年同じですか?
- 流行している感染症の影響は受けてはいませんか?
解析データや動向に関する情報を得ることである程度の分析をすることはできますが、毎年同じ状況じゃないと完全なる比較が難しいこと、前述の変化の影響があると数値の変動も大きくなること、これらのことから、解析データで一喜一憂することはストレスの元にしかなりません。
検索エンジン最適化、検索エンジンマーケティングはWebマーケティングの施策(手法)の一つでしかないことを心得て、アルゴリズム(システムの計算方法、処理手順)の変化の影響と市場の変化の影響を調査し、変化に合わせて対応するための方針を決めて検証して改良に努めていくために解析データを目安・参考用として使うことをお勧めします。
SEOの基本的なやり方3「SEOに取り組む」(ただし、SEO自体はできることが限られていること、成果が実感できるとは限らないことを留意する必要がある)
「検索エンジンに人間と同じように内容を理解してもらえるように対策すること」として、何ができるのか。
SEOとしてやることは何か。
正直、やれることはあまり多くありません。
それでは、「SEOでやること」とは何でしょうか。
当方の今までのホームページ(Webサイト)に関わってきた経験とSEO・SEM(検索エンジンマーケティング)の経験から、下記のように「ユーザーに対してではなく、検索エンジンのみに対して行うこと」だと考えています。
具体的なやり方についても説明またはヘルプページの外部リンクを貼っていますので、よろしければ、ご参考ください。
- XMLサイトマップ(sitemap.xml)を設置する(具体的なやり方)
- Google Search Console(Bingの場合はBing Webmaster Tools)からクロールリクエストをする(Google Search Consoleを使った具体的なやり方、Bingは大体SearchConsoleと大体同じやり方で対応できるので省略)
- パンくずリストを設置する(具体的なやり方)
- 検索対象外のページや「ユーザーにとっては必要だけど検索流入は意図していない」コンテンツに対してnoindexの処理をする(具体的なやり方)
- SEO評価のリスクがあると思われる外部ページへのリンクにnofollowをつける(特に広告リンク)(具体的なやり方)
- 構造化データをサイト・ページに設置する(具体的なやり方)
- ドメインのWhois情報を会社・お店(事務所)の情報にする(具体的なやり方)
- 悪質なところ(事業やサービスに関係がないだけではなく、良いサービスであると紹介されたわけではないものやスパム等の明らかに真っ当なサイトではないもの)ところからの被リンクの否認をする(具体的なやり方)
なお、以下の要素については、それぞれ考えがあり、上記の一覧からは除外しています。
メタディスクリプション(meta description)を整える
メタディスクリプションを見て「ホームページを見てみようかな」と判断するのは、検索エンジン(機械)ではなく人間のためであることから、「SEOではありつつも、SEMの一部である」と判断して除外しています。
WordPressのテーマまたはプラグインで設定することができます。WordPress以外の場合は、大体のツールやサービスで機能として備わっています。
robots.txtの設置をする
検索エンジン用のクローラーに対してホームページ(Webサイト)の閲覧ルールを伝えることもSEOの一つであるとは言えるものの、今までのSEO・SEMの研究結果から、robots.txtは「このページはログインが必須でクロールしてほしくないページ(フォルダ)です」と伝えるために使うのが主な用途になり(インデックスのルール指定はnoindexがある)、自身のサイトの品質を上げるために設定する類のものではないと考えたため、除外しています。
ファイル自体は実在していないのですが、WordPressをインストールすると、仮想robots.txtが出力されます。「wp-admin」以下のディレクトリへのクローラーの巡回をブロックしています。
具体的にどのように対応するのか
HTMLでコーディングするケースの場合は、ホームページ制作のプロにご相談ください。
ここでは、WordPressやホームページ制作ツール・サービスの場合について説明します。
ご自身で調べながら対応することが難しい場合は、詳しい方にご相談いただくことをお勧めします。
XMLサイトマップ(sitemap.xml)を設置する
WordPressであれば、デフォルトで「wp-sitemap.xml」が生成されます。プラグインでWordPressが生成したもの以外の「sitemap.xml」を生成して使う対応も可能です。また、XMLサイトマップについては、WordPress以外でも大体のツールやサービスでxmlの生成が可能です。
パンくずリストを設置する
WordPressの場合はテーマで対応しているものもありますが、プラグインを使って実装することもできます。WordPress以外の場合は、大体のツールやサービスで機能として備わっています。
noindexの処理をする
WordPressの場合はテーマで対応しているものもありますが、プラグインを使って対応することもできます。WordPress以外の場合は、大体のツールやサービスで機能として備わっています。
ただ、noindexについては10年以上のSEO対応経験から、間違えると検索結果から削除されたまま復活しにくい状況になってしまうことは否めませんので、noindexの処理については慎重に対応した方が良いでしょう。そのため、Google Search Centralのnoindexについて説明するページを読んでも分からない場合は、SEOについて詳しい方に対応をご依頼いただくことをお勧めします。
SEO評価のリスクがあると思われる外部ページへのリンクにnofollowをつける
WordPressの場合はデフォルトの機能で備わっています。
WordPress以外でも大体のツールやサービスで機能として備わっているはずですが、当方では未確認なので、ツールやサービスのヘルプページで「nofollow」についての情報がないかをご確認いただくことをお勧めします。
noindex程ではありませんが、nofollowについては10年以上のSEO対応経験から、間違えて設定してしまうと正しく評価を得られにくいのは否めませんので慎重に対応した方が良いでしょう。そのため、Google Search Centralのnofollowについて説明するページを読んでも分からない場合は、SEOについて詳しい方に対応をご依頼いただくことをお勧めします。
構造化データをサイト・ページに設置する
WordPressの場合はテーマで対応しているものもありますが、プラグインを使って対応することもできます。WordPress以外のツールやサービスについては当方では未確認なので、ツールやサービスのヘルプページで「構造化データ」についての情報がないかをご確認いただくことをお勧めします。
ただ、構造化データを正しく設定する場合は構造化データについての正しい知識が必要になります。自前で対応する際の補助的なツール(スキーマ マークアップ検証ツール)はありますし、ガイドもありますが、日本語で各項目を説明しているページは多くはなく、分かりやすいとは言えず、設定も難しいです。少なくとも、構造化データに詳しい人以外はスムーズに対応するのは容易ではありませんので、構造化データについては自前で対応せず、構造化データの対応ができる専門的な知識を持つ方に対応をご依頼いただくことをお勧めします。
ドメインのWhois情報を会社・お店(事務所)の情報にする
公開できる情報で店舗や事務所もあるのにWhois情報をドメインサービスの運営元会社を代理公開しているのは、実在している店舗や事務所であることを証明できないので勿体ない行為です。可能なら、Whois情報をきちんと設定しましょう。
ですが、Whois情報の変更はWordPressやホームページ(Webサイト)制作ツール・サービス側では対応することができません。ドメインを購入・更新しているサービスサイト側で対応する必要があります。
ご利用のサービスのヘルプページに「WHOIS情報の変更・確認方法(または設定)」のようなページがあるはずなので、ご確認の上でご対応ください。
ヘルプページを見ながらであれば難しいことはないはずですが、英語表記のところでつまずきやすいと言えますので、不安な方は、ドメインの設定代行をしている人に対応をご依頼いただくことをお勧めします。
被リンクの否認について
基本的には、相手の管理者に被リンク(リンクを貼っているもの)を解除してもらうように申請することが前提となっていますが、スパムのような真っ当なサイトではない場合、管理者が対応してくれるとは限りません。そういうときに、被リンクの否認ツールがある場合は、否認ツールを使って対応をします。
Bingの場合は、Bing Webmaster Toolsに「否認ツール」という機能があったようなのですが、2025年10月10日現在は機能があることの確認ができませんでした。
Googleで被リンクの否認については可能ですが、被リンクが真っ当であるかどうかの判断は容易ではありませんし、慎重に対応する必要があります。
対応方法は、Google Search Consoleのメニューにはなく、ヘルプページに貼ってあるリンクにアクセスして、専用の書き方で書いてあるテキストファイルをアップロードすることで対応するのですが、やり方も専用の書き方が見慣れないと難しいと感じるかと思いますので、Google Search Consoleの「サイトへのリンクを否認する」ページを見ても分かりにくいと感じたり、不安な方は、詳しい人に対応をご依頼いただくことをお勧めします。
SEOができても成果が出るとは言い切れない……
残念ながら、SEOができたからといっても成果が出るとは言い切ることはできません。
何故なら、SEOを行い、検索エンジンがページの評価をより正確にできるようになったとしても、実際に成果につなげるためには、SEM(検索エンジンマーケティング)が必要であり、SEMも検索システム自体が性質上「ユーザーが検索する」ことで成り立つために万能ではありません。また、Web上には、様々な優れたホームページ(Webサイト)があり、競合のホームページ(Webサイト)が強ければ、検索順位の上位を目指すことは困難とも言えます。
更に、Google検索等の検索エンジンのアルゴリズム(システムの計算方法、処理手順)は全て公開されているわけではありませんので、経験やデータから分析することはありますが、仕組みを完全に解析して対策することは難しいと言えます。
SEO・SEMのデメリットをまとめると次の通りです。
- 需要が低い・知名度が低いものに対しては弱い(正確には検索されないので流入数が増えにくい)
- 専門家がコンテンツを提供している・古くからコンテンツを提供しているなど競合が強ければ、検索順位で上位になる(勝てる)確率が下がる
- 効果が出るまでに時間がかかる
- 検索エンジンのアップデートや手動で対処されることによる順位下落や検索結果に表示されなくなるリスクがある(ただし、悪質なことをせず、適切に情報を発信していれば問題ありません)
そのため、この一つの施策(手法)だけを行って満足してしまうことはお勧めできません。アルゴリズム(システムの計算方法、処理手順)の変更や不具合により検索結果からの流入が急激に減少してしまうと、他からの流入がないので、その間、成果を得られなくなってしまいます。
一つの施策(手法)だけに頼る怖さを知らなくても、一つの施策(手法)だけに頼ると、その施策(手法)が何らかの外部要因で使えなくなったときに困ることがあるというリスクは知ってほしいなと思います。
SEOの基本的なやり方4「焦らずに待つ」
SEO・SEMに限らないのですが、マーケティング手法ですぐに効果が出るものはほぼありません。
特に、SEO・SEMに関しては、検索エンジンがクロール(クローラーと呼ばれるプログラムがWebページを巡回、情報を収集すること)するタイミング、評価を行い、検索結果に反映するタイミングは「公開・更新したすぐ」ではありません。そして、どのWebサイト(ページ)でも同じではありません。間隔は数日~数週間とWebサイトによって異なります。
だからこそ、成果が出なくて焦っている気持ちや、成果が早く出てほしいと気が急いてしまう気持ちは分かりますが、このように反映には時間がかかるものなので、公開した当日・翌日で判断することは危ないです。
早くて数日~遅くて数週間はかかるものなので、最低でも1週間は待つことをお勧めします。
また、変化が生じても落ち着くまでに時間がかかります。今までのホームページ(Webサイト)に関わってきた経験とSEO・SEM(検索エンジンマーケティング)の経験から、全く動きがないまま1週間~1ヶ月ほど経過している場合は、どこかに問題があるのか疑った方が良いのですが、動きがある状態で落ち着くまでには、数ヶ月ほどはかかります。Webサイトの元々の状態によっては目に見える形で成果を実感するのに半年くらいはかかる場合もあります。対応状況次第では1年かかることも留意した方が良い場合もあるでしょう。
このことからも、反映に時間がかかることから対策は早めに取った方が良いのですが、対策を取った後は焦らずに待つ必要があるものです。
「SEOは中長期の取り組みのために時間コストが高い施策(手法)である」と覚えておきましょう。
対策をしたので放置しても良いと言えず、一昔前に比べて今はブログ記事だけ取り組めば良いとも言えない分、SEO・SEM(検索エンジンマーケティング)だけならず、ホームページの専門的な知識や技術が求められるようになったために、対応コストは低くはないので、今となっては他の施策に比べて大変なのかもしれません。マーケティングの知識がないと対応できなくなったのは、それだけ検索エンジンが改良して良くなってきたとも言えるのですが……。
【まとめ】SEOだけじゃなく、様々な施策(手法)でホームページ(Webサイト)への流入数を増やして、成果につなげていきましょう!
今回の記事の大半が「SEO以外でやるべきこと」の話になっている通り、SEOはWebマーケティングの施策(手法)の一つだと捉えることが成果に結びつけるためには重要であり大切なことです。
是非、本記事の内容を基に「ホームページ改善・マーケティング計画書の作成(既にある方は計画書の見直し)」にお役立ていただけましたら幸いです。
作った(見直しした)計画書は、一度にすべて取り組むものではありません。1ヶ月に対応できる部分で区切って少しずつ、中長期的に取り組むものです。お急ぎの方は専門にしている業者にご依頼いただくことをお勧めします。
SEO・SEMに限らず、様々な施策(手法)でホームページ(Webサイト)への流入数を増やして、成果につなげていきましょう!
【余談(おまけ)】AIモード(AI検索)に対する対策(特にllms.txt)についてはどうなの?(個人的な主観もあります)
Google検索に追加されたAIモードや、検索結果画面の上部に表示される「AIによる概要」の他、GoogleのAIアシスタントである「Gemini」など、AIを活用したサービスやシステムが増えてきました。
AI(人工知能)を便利に活用することで、様々なことが効率的に対応できるようになり、状況によってはAIを使わないことは当たり前であり推奨されることも。
だからこそ、「AIに対する対策は必要なのか?」と気になることもあるかと思います。
ただ、AIは仕組み上、情報がないと対応できません。では、その情報はどこから手に入れているのか。
それは、ホームページ(Webサイト)などのWeb上で公開されているデータです。
だから、良質なホームページを作り、適切にSEM(検索エンジンマーケティング)・SEO(検索エンジン最適化)に取り組んでいれば、自ずとAIに対しても効果的に働くはずです。
LLM(大規模言語モデルと呼ばれる。Large Language Modelの略称)技術を基に構成されたAIのサービスが増えていることから、「LLMに対して対策した方が良いのではないかも」「GEO(生成AI搭載検索エンジンでのコンテンツ引用の最適化)に取り組んだ方が良いのかも」と、この記事を読んだ方は気になっているのではないでしょうか。
実際にLLMに向けた設定ファイルである「llms.txt」を活用した手法やGEOについても情報が出てきているのも事実です。
ただ、GEOやLLMに対する最適化・対策は「SEO」と言えるのでしょうか。検索という用途は同じだとしても、相手は検索エンジンのクローラーではなくAIになることから、SEOではなく、それぞれの用語があるのなら、それぞれの用語として認識して別物として取り組んだ方が良いです。
そして、今すぐに対策が必要か不要かで言うなら、情報の誤解・誤った引用を防ぐため、逆に正しい情報を引用されやすくして露出を増やす効果を狙いたいためであれば「今すぐに対応した方が良い(必要)」と言えますが、AIの仕組み上、AIに分かりやすく情報を伝えないと効果が出るとは考えにくいことから、分かりやすく情報を整えられている人以外は「現時点では不要」だと考えます。
実際、まだ新しい技術であり、2025年時点では実装を支援するツールが出てきてはいるものの標準化されている仕様とはまだ言えず、標準規格として業界でサポートがしっかりしているとは断言が難しい状況にあります。
そのため、優先度としても高いであろうSEM・SEO、その他の施策(手法)について検討して取り組み、現時点で打てる手は打ったというときに取り組んでも問題はないのではないでしょうか。そして、「AIで自身(自社)の情報を使われてほしいのか」「ご自身の事業やサービスはユーザーがAIでおすすめを確認するものなのか」を考えたときに「確認する」と考えられると判断したのであれば、対策を検討するというのが良いかと思います。
まずは、情報を分かりやすく、人間にも機械にも伝えられるように整理してから、AIに対して必要なら対策することを考えてみてください。